4/15に情報処理試験(プロジェクトマネージャ)を受験してきた。受験までの活動について振り返っておく。1か月半という短期間での学習はある程度成功し、午後Ⅱを書き切り勝負に持ち込むところまで到達した。
学習開始
試験に申し込んだものの、2月はバグ対応に追われて殆ど学習ができなかった。3月に入り、仕事が少し落ち着いたので学習を開始した。
情報処理試験を受けるのは5年振りのため、午前Ⅰから受ける必要がある。しかし、今までの活動の中で知識は蓄えられているだろうと考え、午後Ⅰ→午前Ⅱ→午後Ⅱ→午前Ⅰの順で学習することにした。
書籍は本屋でたまたま見かけた以下を買った。
2017 プロジェクトマネージャ「専門知識+午後問題」の重点対策 (午後試験対策シリーズ)
午後Ⅰの学習
まずは1年分の過去問を解いてみた。しかし、思うように回答が書けず、また解答の表現が腑に落ちなかったので、過去問を解き続けても点数が伸びないと考え、書籍を使って学習することにした。問題は過去問から抜粋した15問あり、丁寧な解説がついている。解いていくとだんだん慣れてきたようで、15問を終えると合格点がとれそうな感触が出てきた。
午前Ⅱの学習
午前Ⅱは書籍を読んで知識を増やした上で、過去問を解いた。3回くらいやったが、70%を越えるくらいの得点がとれることが分かったため、対策を終了した。ここまでで3月が終わろうとしていた。
午後Ⅱの学習
まずは書籍を読んでみたが、全く書ける気がしなかった。実験結果を論文(レポート)にするのとは全く違うと感じた。そこで、ネットを調べたところ、概要設計を先にすべきとのことであった(書籍にも同様のことが書いてあったが無視していた)。また、ストーリーは適当に作るべしとのことであった。
そこで1時間を掛けて、とにかく概要設計を書き切ることにした。実際に自分がプロマネとして活動した内容を書いてしまうと、苦労話が多くなり、試験にパスすることに向かないとわかってきた。そのため、自分がメンバーとして入ったプロジェクトや午後Ⅰの話も参考にしてそれらしいストーリーを作り、書き切る方針にシフトした。何も思い浮かばなくとも1時間は着手することで、話を捻り出して書き上げる訓練をした。
概要設計がそこそこ書けるようになったので、テキストエディタで文字数をカウントして全文を書いてみた。何回か書くと、文字数の規模感と概要設計の精密さの関連が分かってきた。あと数日しか残っていなかったので、原稿用紙で回答を作成し、本番のシミュレーションをした。
午後Ⅰの学習
午後Ⅰは過去問が解けるWebサイトを利用した。2回やってみたところ、どちらも70%を越えたので対策を終了した。とにかく午後Ⅱ対策に時間を掛けなければならない。
試験へ
試験前日に午後Ⅱを2回分原稿用紙に書いたので、腕が筋肉痛にならないよう湿布を貼ってから寝た。午後Ⅱに不安を感じていたが、試験日が来てしまったので、あとは運を天に任せることにした。
<つづく>
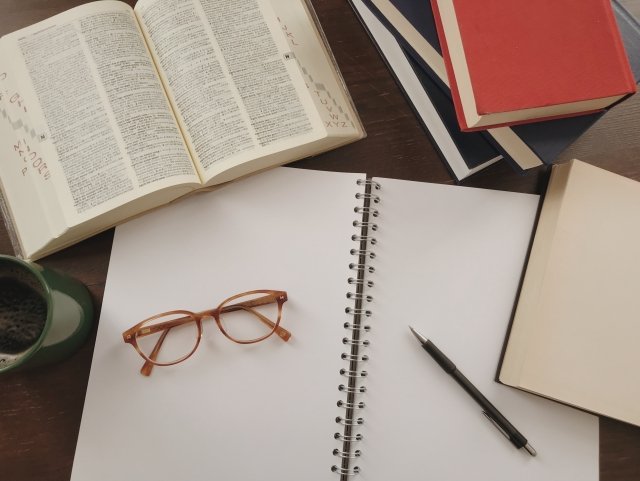

コメント